
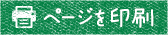
生活や仕事に関係する支援制度成人
この内容は2024年7月時点のものです。
国や自治体から、見舞金や保護費を支給される制度があります。また、病気のために仕事を休まなければならなくなったり、仕事ができなくなったりした場合に利用できる支援制度があります。
生活に関する支援制度
-
特定疾患見舞金制度
- 「指定難病」と認定されて治療を受けている患者さん、またはその保護者の方を対象に、市区町村より見舞金が支給される制度があります。
- 【参考例:習志野市の場合※】※:条件により異なります。
入院患者(15日以上):月額12,000円(生活保護受給者は8,000円)
通院患者:月額6,000円(月1日以上)
- 注)自治体によっては制度自体がない場合があります。また、制度の名称やその見舞金額、給付方法もさまざまです。詳しい条件などは、お住まいの市区町村の役所窓口にお問い合わせください。
-
障害年金
- 各種年金に加入している間に初診日のある病気により日常生活に支障を来たすようになった場合には、障害年金を受給できる場合があります。受給には法令により定められた障害等級の1級から3級(障害基礎年金は1級または2級)までの認定が必要です。支給額などの相談や申請については、各担当窓口にお問い合わせください。相談だけでしたら、お住まいのお近くにある年金センターでも可能です。
-
| 年金の種類 |
| 国民年金(自営業、農業・漁業に従事している方) |
障害基礎年金(各市町村) |
| 厚生年金(企業に勤めている方) |
障害厚生年金(年金事務所) |
| 共済年金(公務員などの方) |
障害共済年金(各共済組合) |
-
生活保護制度(生活費に困窮した場合)
- さまざまな制度などを活用してもなお生活に困窮する場合、国で定められた基準により計算される最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。詳しくは、厚生労働省のホームページの「生活保護制度」をご確認いただくか、またはお住まいの地域の福祉事務所にご相談ください。
-
障害者福祉に関する支援制度
- 障害者福祉に関する支援制度には、下記のものがあります。
-
障害者手帳を取得した方への支援の一例
- 自動車税免除
- 交通機関の割引制度
- 自立支援給付(障害福祉サービス・補装具など)
- など
-
就労に関する支援制度
傷病手当金(会社を休まなければならない場合)
- 被用者保険(職域保険)に加入している方は、1つの病気やけがにより会社を休んだ場合、連続して3日間会社を休んだ後、4日目以降から休んだ日に対して標準報酬日額の2/3に相当する金額が、健康保険組合より支給されます。受給期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月間です。
退職すると健康保険の被保険者の資格を喪失しますが、次の一定の要件を満たした場合は、退職後も支給開始から1年6ヵ月を限度に傷病手当金が支給されます。
- ❶ 被保険者の資格を喪失した日の前日までに引き続き1年以上被保険者であったこと
❷ 資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている、または受けられる条件を満たしていること
- 注)退職日に出勤した場合は、継続給付を受ける条件を満たさないため、資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金は支払われません。
-
失業給付基本手当(退職後の手当)
- 失業した場合に求職活動をする間の生活の安定を図ることを目的とした給付で、雇用保険加入期間による受給資格要件を満たす場合に受け取ることができます。給付される日数は、離職理由、年齢、被保険者期間により異なります。失業するまで勤めていた就労先やハローワークにご相談ください。詳しくは、厚生労働省職業安定局のホームページの「基本手当について」をご確認ください。
-
就労支援の利用
- ハローワークや障害者就労支援センターでは、職業紹介を受けることができます。最寄りのハローワークに登録する際には、「医療受給者証」や「医師の診断書」などを提出してください。
-
難病患者さんのための就労支援
-
難病相談支援センターによる就労支援
- 各都道府県に配置されている「難病患者就労コーディネーター」が、就労に関する悩みや疑問について患者さんからお話を伺ったうえで、アドバイスをしてくれます。必要に応じてハローワークへ同行訪問し、職業紹介が円滑に進むよう支援を行います。
-
ハローワークによる就労支援
- 障害者の専門援助窓口に「難病患者就職サポーター」を配置し、難病相談支援センターと連携しながら、就職を希望する難病患者さんの症状や特性を踏まえて、きめ細やかな就労支援や、在職中に難病を発症した患者さんの雇用継続等の総合的な就労支援を行います。
また、ハローワークは一度登録すれば、全国どこのハローワークでも利用できます。
-
民間企業による就労支援
- 民間企業にも、障害のある方の就労をサポートしてくれる会社があります。求人紹介のほか、ビジネススキル向上のためのワークショップなどを開催している会社もあります。
-
登録者証*
- 福祉や就労などの支援をスムーズに利用できるよう、指定難病であることを証明するもので、医療費助成の対象とならない方にも交付されます。原則としてマイナンバー情報連携を活用するため、マイナンバーカードが登録者証になります。ただし、マイナンバー情報連携を活用することができない状況にあるときは、紙による発行も可能です。
申請方法や登録者証の発行方法は、自治体により異なりますので、詳しくは、お住まいの都道府県・指定都市の窓口にお問い合わせください。
-
*:令和6年4月1日より施行
- 特定求職者雇用開発助成(難治性疾患患者雇用開発助成)制度というものを聞いたのですが、どのようなものですか?
-
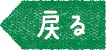
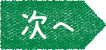
![]()
