

患者さんとご家族の声
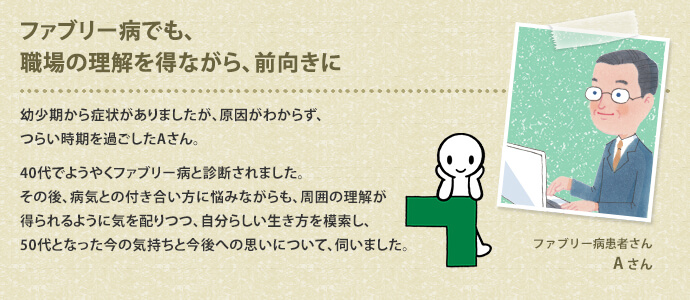
家族にも理解されなかった幼少期

- 幼稚園から小学校くらいのとき、手足のあまりの痛さに、噛みちぎりたくなるような衝動に駆られるほどでした。後に、母親もファブリー病だったとわかったのですが、幼少期に「熱があると痛いのは、みんな同じ」と言われ、厳格な父親からは、ひ弱や軟弱と言われることもあり、辛い日々を過ごしていました。
- 学校生活では、体育の授業で足が痛くなったときは見学することとなり、自分だけがぽつんと座っているのが寂しく、友達と同じように運動できればといつも思っていました。
心臓の症状からの診断
- 20代前半のときの健康診断で、心臓が少し大きくなっていると指摘されたときは「スポーツ心臓みたいなものでしょう」と言われ、結果的に経過観察となっていました。その後、40代のときに肥大型心筋症や僧房弁閉鎖不全症と診断され、心臓の薬を飲み始めるようになりました。
それからしばらくして、転勤することとなり、新たに病院を受診したところ、「ちょっとおかしいから調べてみようか」と先生が精査してくれたのがきっかけで、ファブリー病の診断に至りました。
ファブリー病への理解が深まれば、また道は開ける
- 妻と幼い子どもがいるので、診断がついた後はこれからのことが一番気になりました。「これから病気とうまく付き合っていかなければ」と思うのと同時に、生活の幅が狭まってくるのではないかという不安もありました。以前は外回りや出張、接待などもある営業職だったのですが、先生からは「営業はストレスもかかるし、職種を変えたほうが良いよ」と勧められました。
その後、会社の方とも相談し、内勤の仕事に変わりました。それまでは営業で結果も残してきたので、職種が変わったときには、昇進を諦めざるを得ないことが悔やまれるところでした。
- 現在では上司の理解もあり、具合が悪いときや、治療で通院が必要なときには有給休暇を取りやすい環境に感謝しています。
私自身としては、朝礼の機会などに「耳が聞こえづらいので、返事をしないときがあっても、無視しているわけではないので」などと軽く伝えて、不快感を与えないように気を付けています。一方で、手足の痛みなどで会社を休むと、さぼっていると思われるケースもあるようなので、これから先、より多くの方にファブリー病のことを知っていただき、理解が得られやすくなればと切に願っています。
※この内容は2018年10月時点のものです。
![]()

