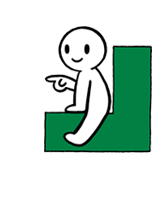一瞬の安心と大きなショック ―ムコ多糖症Ⅱ型との診断
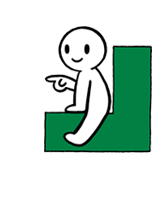
- 息子のMは、わが家の次男として生まれました。1歳になっても寝返りができず、支えて座らせてあげる状態で、長男との成長の差は明らかでしたが、かかりつけの小児科の先生からは個人差の範疇だと言われました。
- その後、1歳半頃に立って歩けるようになり言葉も発するようになったのですが、2歳半頃に病院の療育施設でリハビリを受けていたとき、そこでお会いしたムコ多糖症のお子さんをもつお母さんに「この子はきっとムコ多糖症だよ。診てもらいなさい」と言われました。
- 同じ頃、小児科に週1回勤務していた発達やリハビリの先生からも、ムコ多糖症かもしれないというお話がありました。そして、大学病院に紹介され検査の結果、ムコ多糖症Ⅱ型であることが分かりました。
- 成長の個人差だと言われ続けている間も「単なる個人差ではない。きっと何かあるはずだ」とは思っていたので、診断がついたとき「やっと病名がついた、やはり病気だったのだ」という安心はありました。
- でも、それは一瞬のことで、診断された病気がどういう病気なのかよく分からず、そして主治医から、20歳まで生きるのは難しいだろうと言われ、ショックを受けました。帰り道のことは何も覚えていないくらいでした。もちろん妻も同様で、本当にどうしてよいのか分からない、そんな状態だったと思います。
「ひとりじゃないんだ」―患者さん同士のつながり
- 息子の今後の生活と治療のことを考えたとき、私たちはできるだけ色々な人に話を聞きたいと思いました。とにかく知りたいことがいっぱいあり、無我夢中でした。「日本ムコ多糖症親の会」という患者家族会に入り、その名簿から会員の方に連絡をとり、お会いして話を聞かせてもらいました。
- 希少な病気であるムコ多糖症ですが、私が住む市には、わが家を含めて4家族に5人の患者さんがいました。この環境は、今にして思えば恵まれていたとさえ言えるかもしれません。インターネットなどで調べられないような普段の生活をどう過ごしているのかが特に知りたいと思うことでしたし、それには先輩の話がとても参考になります。本当に、周りの方々に助けてもらった、という気持ちが大きいです。
- テレビの深夜番組でムコ多糖症について取り上げられたことなどがきっかけで、支援の輪が広がりました。病気に縁のない若い方たちが関心をもってくれて「何かできることはないか」と活動を始めてくれたこと、そういうつながりができたことをとても嬉しく感じました。ある患者さんの家族の方が「ひとりじゃないんだ」と言われたのが、とても深く印象に残っていて、今では私自身の気持ちを支える言葉として大切にしています。
※この内容は2013年12月18日時点のものです。
![]()